小倉コレット井筒屋がついに今週閉店に・・・。

こんばんは!
何かが去っていくという事はとても寂しい事です。
今月末に小倉駅周辺の新たな象徴として約10年活躍してくださった「小倉コレット井筒屋」さんがいよいよ閉店となります。
家賃交渉が上手くいかなかった事が閉店の主な要因だという事です。
私は、愛知県名古屋市東区・三重県四日市市鵜の森で生活した事がありますが、主要駅の周囲の大型百貨店が閉店した後の影響の大きさを痛感しています。
名古屋市は大きな街で、閉店開店が当たり前に行われ、空き店舗もすぐに埋まるほど人の出入りが活発で、主要駅周辺の高層化も功を奏した形になり大手百貨店である高島屋・近鉄百貨店なども安定した集客を可能としています。
名古屋市画像 出典元:名古屋市役所
対して、四日市市は三重県内では一番の人口を誇ってきた訳ですが、いつからか郊外のイオンなどに集客を狙った結果、人の流れが分散され主要駅周辺は閉店が相次ぎ、しかし開店にこぎつける店舗は少なくアムスクエアなどの象徴店舗の撤退でさらに加速度的に駅前アーケードが衰退していきました。
四日市市画像 出典元:タウンフォトネット
私の中では皆さんとは考えが大きくかけ離れているかもしれませんが、人の流れは大きく多彩な百貨店を中心に集客を可能にするものだと思っています。
そんな中で、一定の集客をコレット井筒屋・井筒屋本館別館がになってきた事は否めない事実ではないかと思います。
コレット井筒屋からアーケードを横切り井筒屋本館を経由し、橋を渡ってリバーウォークへ・・・。
この流れが大きくアーケードを支えて来たように思うのです。
データではアーケードの収益は減衰傾向との話もありましたが、果たしてコレット井筒屋の集客が失敗していることになるのでしょうか?
実際に空き店舗やコミュニティ場所だったらどうなっていたでしょうか?
そうした事を考えるとき、コレット井筒屋の役目は非常に大きかったのではないかと考えます。
閉店セールには多くに人が訪問しておられました。
エスカレーターで前のお客さんは「寂しくなるのかな?この街・・。」と話していたのが聞こえました。
現在のところ次の店舗の決定の話はまだ無く、ランドマークとしての構想も提示されてはいないように記憶しています。
これから迷走しているうちにアーケードが衰退していかない事を切に祈りたいです。
さて、地元に根付いて支えてきた井筒屋さん以外で、小倉駅の未来を託せる百貨店は果たして存在するのでしょうか?
パルコやロフト、ドンキなどの専門的店舗では役不足ですし、コミュニティ施設では集客は偏ります。
かと言って、高島屋・三越・大丸などのような大きな百貨店は地元密着型のコレットが撤退した後には参入はしないでしょう・・・。
ならば北九州市と商工会議所はどこにその触手を伸ばすのでしょうか?
正直、私はコレットとの再交渉で将来見込みを対話しての平和解決を望みたいのですが・・・。
それはもう叶わない事なのでしょうね・・・。
四日市市は人口30万人の都市でした。
名古屋市は230万人。
北九州市が現在100万人です。
集客の観点からすれば放っておいても四日市市を超える集客は見込めるでしょうが、アーケードは放っておけば減収に敏感に反応し撤退店舗が出始めてしまいます。
体力のある都市ですが、負の連鎖のキッカケに繋がってしまわない事かが心配です。
新たな都市開発の象徴に次なる施設がなります事を願います。
コレット井筒屋さん・・・これまでの10年間お疲れ様でした。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
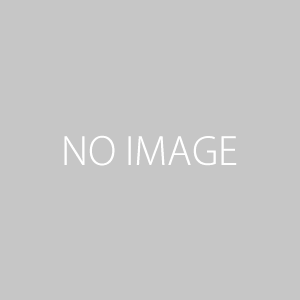




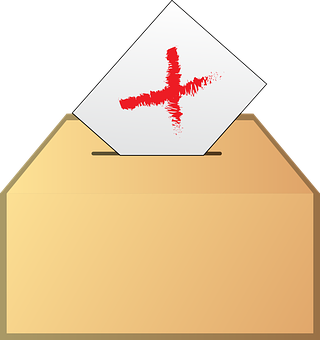


この記事へのコメントはありません。